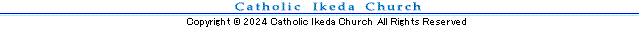| 2025年2月 | ▶︎朗読を聞く |
あなた方の抱いている希望について説明を求める人には・・・
-ペトロの第一の手紙、3章15節-
-来住神父-
・・・・・・・・・・・・・・
長いセンテンスの冒頭です。「あなた方の抱いている希望について説明を求める人には、いつでも弁明 できるように 備えていなさい。」
これは、イエス・キリストの弟子の一人であるペトロが、キリスト教信仰を共にしない人と対話をする時の心得として示したものです。
ネットでは宗教を軽視する人の声が目立ちます。しかし実生活では、よい機会があれば、宗教について何か知りたいと思っている人は結構います。 ただ下手に質問すると、シツコクつきまとわれそうなので、ためらっているのです。
一方、キリスト者の側とは、自分の信仰について知ってほしいのはもちろんですが、「キリスト教とは何か」ということは複雑な話題です。日頃から準備している人でなければ、話し出せないのです。
キリスト教に少し興味のある人から出てくる質問で多いのは、「神父と牧師とはどう違うのですか」というものです。 この質問は「神父は結婚できないが、牧師は結婚できる」 と答えることができるので、キリスト者には歓迎されます。 しかし、ここから「キリスト教とはどういう宗教か」 という本質につながることはほとんどありません。
「カトリックとプロテスタントはどう違うのですか」 という質問もそうです。その違いはキリスト者にとっては大事ですが 、キリスト教についてほとんど知らない人にとっては意味がありません。
そう考えると、ペトロがキリスト者と、 その信仰を共にしない人が相互理解のために対話しようとするときの話題として、 「あなたが抱いている希望」を持ち出したのは大いに意味のあることです。 キリスト者にとっては、「キリスト教とは何か」「何を信じているのか」 ということよりも、「キリスト者は何を希望しているか」ということの方がずっと話し易いからです。
キリスト者に出会うことがあったら、「あなたは、死後の世界があるという希望を持っているのですか」と聞いてみるといいでしょう。「その希望を私は持っています」という答えが返ってくれば、「あなたは死後の世界はどういうものであってほしいと希望していますか」 という質問ができます。
現代のキリスト者は「死後の世界に希望を持っています」とはっきり答えない人も多いかもしれません。 「死後の世界」よりも、「この世の正義」に関心があるからです。 その場合は、「あなたはキリスト教の信仰が、あなたの生き方をどのように良いものにしてくれると希望しているのですか」 と聞いてみると良いでしょう。
「希望」という言葉を用いるのが、 宗教を持つ人と持たない人の対話に適しています。「それは本当か」「それは本当に存在するのか」という白熱しやすい問題を、とりあえず棚上げにすることができるからです。
そして、 宗教を持たない人も、自分の信仰について語ることはできなくても、抱いている希望について語ることができるので、対等に対話することができます。